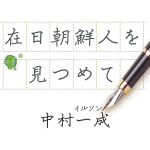vol.26 判決を 紙切れにしない― 京都朝鮮学校襲撃事件から10年
広告

10年間の思いを語る襲撃事件当時の小学生ら(手前、いずれも京都市伏見区で2019年12月22日)
「京都朝鮮学校襲撃事件」の法的応戦は、反差別運動に歴史を刻んだ。「徳島県教組襲撃事件」や、「ヘイトスピーチ裁判」など次の闘いの導線となり、日本司法初の「複合差別認定」や、民対民の差別事件における原告勝訴の流れを作った。京都の闘いは、いわば「次世代の日立闘争」だと思う。しかし、マス・メディアは当初、ほとんどこれを報じなかった。「差別」を主体的に判断ができなかったし、何より極右と関わるのが嫌だったのだ。
風向きは2013年春、ヘイトスピーチの社会問題化に伴い変わる。社会的注目は裁判官にも伝わるし、取材は歓迎すべきだ。だが、当事者と記者の認識には溝があった。そもそも関係者が裁判に託したのは「ヘイトクライムのない社会を」と「民族教育権を保障しよう」の両輪だった。一方、メディアにとって事件はあくまでヘイト問題の原点、それは企業メディアが依拠する多数派の常識でもあった。勝訴に近づく一方でオモニたちの思いが後景に退くジレンマ。高裁判決は日本の司法判断で初めて民族教育の価値を認めたが、「権利」とはしなかった。勝訴が確定した時、前景化した課題は「京都判決を例外にしない」と、「国相手の裁判に勝ち、民族教育権を認めさせる」。具体的には徳島事件と高校無償化裁判の支援だった。…。(続きは月刊イオ2020年2月号に掲載)

写真:中山和弘
なかむら・いるそん●1969年、大阪府生まれ。立命館大学卒業。1995年毎日新聞社に入社。現在フリー。著書に「声を刻む 在日無年金訴訟をめぐる人々」(インパクト出版会)、「ルポ 京都朝鮮学校襲撃事件――〈ヘイトクライム〉に抗して」(岩波書店)、「ルポ思想としての朝鮮籍」(岩波書店)などがある。『ヒューマンライツ』(部落解放・人権研究所)の「映画を通して考える『もう一つの世界』」を連載中。