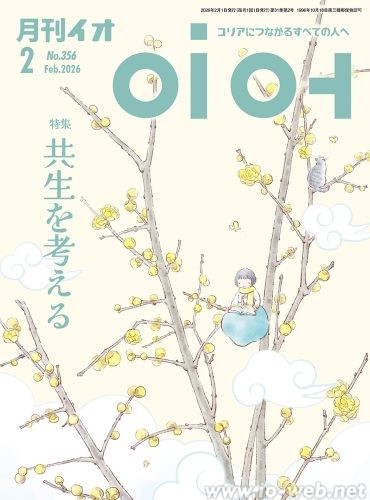ソルニット『暗闇のなかの希望』を読んで
広告
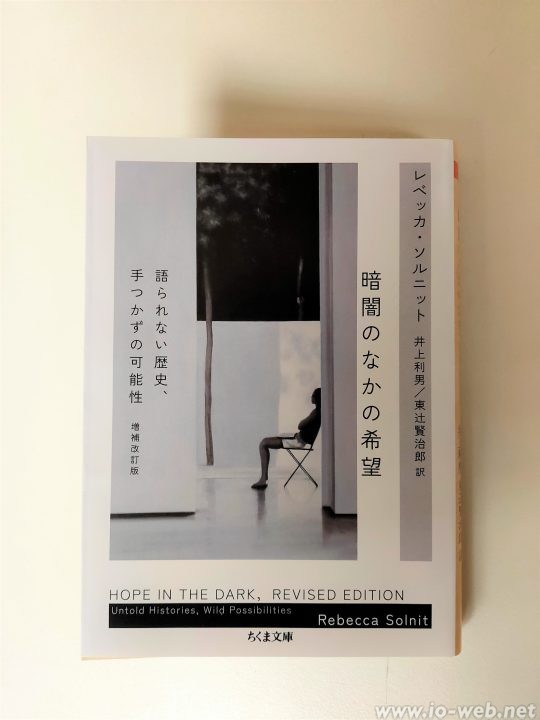
『暗闇のなかの希望 増補改訂版―語られない歴史、手つかずの可能性』(レベッカ・ソルニット著)、井上利男/東辻賢治郎訳、ちくま文庫)
『災害ユートピア』『説教したがる男たち』などソルニットの著作は何冊か読んできたが、熱心な読者ではない。日本で2005年に出版され、16年の改訂版が今回文庫化されたということで初めて手に取った。
原書は2004年に出版された。巻末の小川公代さんによる解説から本書の概要を説明した箇所を引用する。
「レベッカ・ソルニットの『暗闇のなかの希望』は、二〇〇三年に始まったイラク戦争の応答として書かれたエッセイが拡大され、翌年、書籍として刊行された。米国を中心とする有志連合が、国連安保理決議なしの先制攻撃をイラクに対して行い、メディアも政府の武力行使を質すどころかイラクには「大量破壊兵器」が存在することを煽り、「対テロ戦争」という概念を広めていた。世界中に絶望が漂っていたこの時期に「希望を擁護する」ために書かれたソルニットのこの名著は、加筆され、改訂版として二〇一六年に刊行された。本書はその邦訳である」
「未来は暗闇に包まれている。概して、未来は暗闇であることが一番いいのではないかと考える」(本書42ページ)
タイトルにもある「暗闇のなかの希望」というフレーズは、作家のヴァージニア・ウルフの日記からの引用。日記の日付は第一次世界大戦ただなかの1915年1月18日。ソルニットはウルフが言う「暗闇」という言葉について次のように書いている。「彼女は、見通せないという意味で暗闇と言ったのであり、恐ろしいという意味ではなかったようだ。私たちは、これをしばしば取り違える。つまり、未来の不可知性をなにか確かなもの、私たちのあらゆる恐怖の実現、道が途切れた行き止まりと置き換えてしまう」と。
「社会や文化や政治の変化は、予期しない時に、予期しないやり方で起こる。…私たちには何が、どのように、いつ起きるのかはわからない。その不確かさこそが希望の場所なのだ」(35~36ページ)
未来は見通せないが、その不可知性、不確実性(暗闇)の中にこそ希望はある。不確かな現実の中で絶望したり悲観主義におちいったりするのではなく、楽観視するのでもなく、「私たちの為すことに意味があると信じ」続けること。本書でソルニットが言っていることをざっくりと要約すると、こうなるだろうか。
本書で印象に残った箇所のうち一部を以下に引用する。
「あなたの敵は、もう希望はないとあなたが信じることを願っている。無力で、立ち上がる理由もない、もう勝てないのだ、そうあなたが思い込んでしまうことを。希望とはギフトだ。だれにも譲り渡す必要はない。そして力だ。捨ててしまう必要はない」(13ページ)
「希望は、私たちは何が起きるのかを知らないということ、不確かさの広大な領域にこそ行動の余地があるという前提の中にある。不確かさを認識することは、その帰結に影響をもたらせるかもしれないと気がつくことだ。それはあなたが一人でやることかもしれないし、数人、数百万人とともに行うことかもしれない。希望とは未知や不可知のものを受け容れることであって、確信的な楽観主義や悲観主義とは違う。楽観主義者は、私たちが関与しなくても物事はうまくゆくと考える。悲観主義者はその逆だ。どちらも自分の行動を免除する。希望とは、いつ、どのように意味が生まれ、だれや何にインパクトを与えるのかあらかじめわからないとしても、それでも私たちの為すことに意味があると信じることだ。そんなことは事後になってもわからないかもしれない。しかし、それでも意味があることに変わりはない」(19〜20ページ)
「私たちの希望は光を浴びた舞台の真ん中ではなく周縁の暗がりにある」(22~23ページ)
問題山積で混沌とした世界の中で未来をどのように切り拓いていくか、著者は歴史上のさまざまな出来事―それはしばしば断片的なエピソードであったり教科書に載るような歴史ではなかったり、あるいは途中で潰えた物語であったりする―を事例として挙げながらその可能性を論じていく。
絶望や冷笑主義がはびこり、未来への希望を抱くことがナンセンスだといわんばかりの今の時代に、「希望を抱くとはどういうことか」「希望を持つことはいかに可能なのか」をつづる著者の言葉には力がある。
大阪府庁前の火曜日行動、文部科学省前の金曜行動、入管法改悪に反対する国会前のシットインや路上デモ―本書を読みながら、この間取材したり、自らも参加してきた運動の現場、そこで出会った人びとの顔が浮かんだ。
文庫で300ページほどのボリューム。今の時代にこそ読まれるべき一冊ではないだろうか。(相)