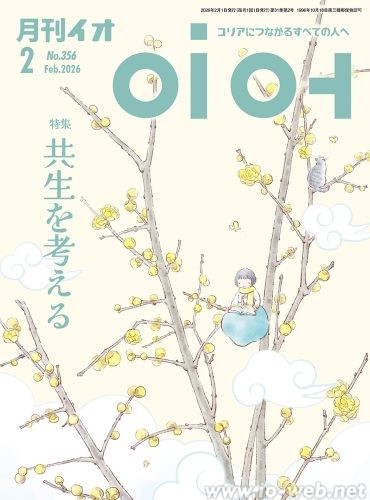2023年の10冊
広告

毎年年末恒例の「私が選ぶ10冊」。2023年は掲載できなかったので、年明けのこのタイミングで書いた。2023年に出版された本の中で面白かった本を10冊挙げる。
①『ナチスは「良いこと」もしたのか』
小野寺拓也、田野大輔著/岩波書店
アウトバーン(高速道路)を建設した、失業率を低下させた、福祉政策を充実させた、などインターネット上で根強く残る「ナチスはよいこともした」という俗説を、ナチズム研究の蓄積をもとに事実性や文脈を検証し、それは誤りである(それは良い政策ではなかった)と明確に指摘した一冊。著者2人はいずれもドイツ現代史の専門家。昨年読んだ本の中で一番を挙げろと言われたらこの本を挙げる。歴史的事実を「事実」「解釈」「意見」の三層に分けて検討する必要性を指摘したくだりを含め、「歴史的に物を見るというのはどういうことなのか」を学ぶことができる良書。歴史を学ぶ学生用の教材としてもいいのではないか。これがブックレットで出版されたことに感謝したい。同じ著者らによる『悪の凡庸さを問い直す』(大月書店)は、ハンナ・アーレントの『エルサレムのアイヒマン』で提示され、アドルフ・アイヒマンを形容したものとして有名になった「悪の凡庸さ」概念を検証した本。こちらもおすすめ。
②『言語の本質―ことばはどう生まれ、進化したか』
今井むつみ、秋田喜美著/中央公論新社
なぜ人間は言葉を持つのか? 子どもはいかにして言葉を覚えるのか? 言語の起源とは? 人間とAIや動物の違いは? 「言語の本質」という壮大な問いを解く鍵として本書が提示するのは、オノマトペ(もぐもぐ、ふわふわ、ぴちゃぴちゃなど「感覚イメージを写し取る言葉」)とアブダクション(仮説形成)推論。認知科学者と言語学者である著者2人が言語の誕生と進化の謎をひも解き、人間の根源に迫る。知的好奇心を刺激するスリリングな一冊。
③『国籍と遺書、兄への手紙』
安田菜津紀著/ヘウレーカ
著者は自分の父親が在日コリアン2世だったことを父の死後に知る。父はなぜそのことを語らなかったのか、自分はいったい何人なのか―。著者のアイデンティティは大きく揺れ動く。手がかりを求めて、資料を取り寄せ、ゆかりの土地を訪れ、交流のあった人の話に耳を傾ける。フォトジャーナリストとして難民、貧困、ヘイトクライムなどの取材を通して、さまざまなの人びとの声を伝え続けてきた著者が自らのルーツに向き合う。そのドラマチックな旅路と著者の真摯な姿に、ページをめくりながら涙した。
④『黙々―聞かれなかった声とともに歩く哲学』
高秉權著、影本剛訳/明石書店
障害者、生活保護受給者、性暴力被害者、難民、失業者…。現代社会でマイノリティと呼ばれる人びと。ある側面から見ると、私たちの社会はこのような人びとから声を奪い黙らせ、抑圧し排除することで成立している。本書はまさにそのような人びとの声を聞くことで本来の意味での「民主主義」の取り戻そうとしている。著者は韓国では著名な在野の哲学者。2008年からノドゥル障害者夜間学校という就学の機会の場を奪われた障害者たちの学校で哲学や文学を教えている。
「世の中に語ることのできない存在はおらず、ただ聞くことのできない存在、聞くことをしない存在がいるのみだ。それゆえ政治的存在として、私たちが投げかけるべき問いは『彼らは語ることができるか』ではなく『私たちは聞くことができるか』である」。
⑤『射精責任』
ガブリエル・ブレア著、村井理子訳/太田出版
昨年7月の出版後、センセーショナルなタイトルもあいまって、各所で話題となった本。著者は米国の人気ブロガー。望まない妊娠はセックスをするから起きるのではない、あらゆる避妊の責任を女性に押し付ける男性が無責任な射精をしたときのみ起きる―本書の主張はストレートだ。
男性の生殖能力は女性の50倍/排卵はコントロールできないが、射精は違う/男性はコンドームが嫌いだというのは、思い込みにすぎない/女性に避妊を期待しすぎている/自分の体にも、男性の体にも、責任を持つのは女性である/男女間の力の差は、簡単に暴力に繫がる/精子は危険である/認めたくないみたいだけれど、男性は自分の肉体や性欲を管理できる
本書に載っている、望まない妊娠による中絶と避妊を根本から問い直す28個の提言の一部を挙げた。どれもあたりまえのことを言っているが、あたりまえの認識になっていない現実がある。男性必読の書。
⑥『笑わない数学』
NHK「笑わない数学」制作班編/KADOKAWA
難解な数学の世界を大真面目に解説するNHKの人気番組の書籍化。天才数学者を苦しめてきた数々の難問を掘り下げながら、数学の知られざる魅力に触れることができる。学生時代、理系科目はてんでだめだったが、サイエンス系のノンフィクションや解説本は好きなので、番組も本にもはまった。
⑦『怪物に出会った日―井上尚弥と闘うということ』
森合正範著/講談社
本物の強さとは、その強さに挑み敗れ去っていった者たちをも輝かせ、かれらの人生にドラマを生み出すものなのだろう。プロボクシングで史上2人目となる2階級での4団体統一王者となった「モンスター」井上尚弥の歩みを、かれと拳を交えたボクサーたちが自らの人生を振り返りながら語る。紹介されるエピソードはいずれも引き込まれる面白さ。切り口、構成も含めて出色のスポーツノンフィクション。
⑧『暗闇のなかの希望 増補改訂版―語られない歴史、手つかずの可能性』
レベッカ・ソルニット著、井上利男訳、筑摩書房
『災害ユートピア』『説教したがる男たち』などの著作で知られるソルニット。日本で2005年に出版され、16年の改訂版が文庫化されたタイミングで読んだ。「希望は光を浴びた舞台の真ん中ではなく、周縁の暗がりにある」。未来は見通せないが、その不可知性、不確実性(暗闇)の中にこそ希望はある。不確かな現実の中で絶望したり悲観主義におちいったりするのではなく、楽観視するのでもなく、「私たちの為すことに意味があると信じ」続けること。絶望と冷笑主義が残りつづける現代に、希望をもつことはいかに可能なのか。著者の言葉に勇気づけられる。
⑨『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン:オセージ族連続怪死事件とFBIの誕生』
デイヴィッド・グラン著、倉田真木訳/早川書房
マーティン・スコセッシ監督、レオナルド・ディカプリオ、ロバート・デ・ニーロらが出演した映画の公開に際して、原作となる本書を文庫化されたタイミングで手に取った。
1920年代のアメリカ南部オクラホマ州。先住民オセージ族が「花殺し月の頃」と呼ぶ5月に起きた2件の殺人。それはオセージ族と関係者20数人が相次いで不審死を遂げる連続怪死事件の幕開けに過ぎなかった。のちのFBI長官フーヴァーは特別捜査官トム・ホワイトに命じて大がかりな捜査を始めるが、解明は困難を極める―。事件は、自らが住む土地から出る石油の受益権によって巨額の富を保有するようになったオセージ族を取り巻き、石油利権と人種差別が複雑にからみあう。米国史の暗部に迫った一冊。これがフィクションではなく実話だということに驚く。
⑩『星を継ぐ者』
ジェイムズ・P・ホーガン著、池央耿訳/東京創元社
個人的にSFでナンバーワンの作品。今回、新版化に際して購入。久々に読み返したが、やはり抜群に面白い。「月面調査員が、真紅の宇宙服をまとった死体を発見した。綿密な調査の結果、この死体はなんと死後5万年を経過していることが判明する。果たして現生人類とのつながりは、いかなるものなのか? いっぽう木星の衛星ガニメデでは、地球のものではない宇宙船の残骸が発見された…」。このあらすじを読んだだけでワクワクしませんか。
(相)