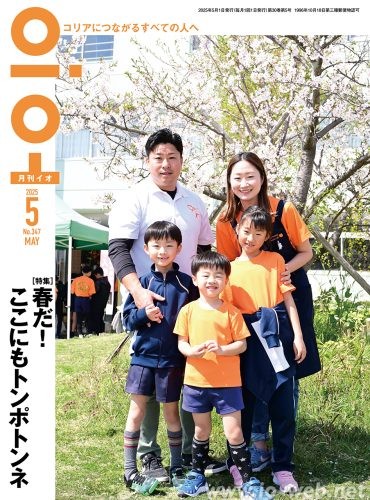夜と朝の間に境界線がないように
広告

提供=©映画『杳かなる』上映委員会
今年1月中旬、映画「杳(はる)かなる」の試写会へ行ってきた。過去に監督の別の作品をイオで紹介していたご縁でお声がけいただいた形だ。
同作は、ALS(筋萎縮性側索硬化症)に罹患した人々の姿と生活、葛藤や心境の変化、周囲とのつながりを3年半の長きにわたって記録したドキュメンタリー。ALSとは、全身の筋力が徐々に弱まり、症状の進行によっては喋ることも困難になる難病だ。
映画制作のきっかけとなったのは、2019年に京都で起こったALS患者嘱託殺人。本人から依頼を受けたとして、主治医ではない二人の医師がALS患者を殺害した事件である。
このニュースが報じられたあと、ネット上では「こんな状態になったら自分も死にたい」「安楽死の法制化が必要なのでは」といった意見が散見された。いかに生きるかよりも、はじめから死へ向かって——それも他人によって勝手に—―議論がなされる状況を食い止めたいとの思いが作品の根底に流れている。
映画は佐藤裕美さんという一人の女性の日常から始まる。車椅子で外出して風景の写真を撮ったり、夫が用意した夕飯を食べたり、パソコンに向かって文章を書いたり、神社にお参りしたり、好きな食べ物を買ったり。その過程に少しずつ、ほかのALS当事者や介助者たちと出会い、孤独、不安、絶望を分かち合いながら、この体で生きることについて考えていく。
筋力の衰えによって声を出せないため、五十音が書かれた透明板を通して目の動きで介助者に言葉を読み取ってもらいながら意思疎通する人。舌がもつれ、以前より不自由が増しても子育てやコミュニティ活動に前向きな姿勢を見せる人。明るい笑顔で人と人をつないだあと、急逝してしまった人…。
少しずつ自由が利かなくなっていく身体。佐藤さんは揺れる思いを刻むため、そして自分が生きた証を残すため、ブログで日記や詩、散文を発信する。作中にもいくつかの詩が挿入されたのだが、それらがとても印象的だったので1編だけ紹介したい。
証
なぜ書くのかと言えば、それが「私が生きていたこと」の証だからである。
それは「私が、私として死んでいくこと」でもある。確かに私は生きていたと
私は私という、個であったと私は、声を失うが、
私は、私以外の誰かが私を語ることを、全身全霊で拒絶する。あいつは、苦しんでいると、不安なのだと
あいつは、虚しかったのだと、絶望していたと
あいつは、もがいていると、許していると
あいつは、幸せだったと、もっと生きたかったのだと語るな。私の声を奪うな。私を利用するな。
私を、いなかったことにするな。戦場で彼は、誰として死なねばならなかったか。
収容所で彼女は、誰として死なねばならなかったか。私は個として、すべてのものから疎外され、峻別されることを望む。
私は 私として、ここに生きて、死んだのだとなぜ書くのかと言えば、それが「私が生きていたこと」の証だからである。
それは「私が、私として死んでいくこと」でもある。
※「書くこと。生きること。:Hiromi’s Blog」内、「証」より引用
作品にはほかにも、たくさんのALS当事者、介助者、家族が登場する。それぞれに違うコミュニケーションの形、方法、流れる時間を、カメラは見守るようにじっと映す。そこには、単なる記号としての“ALS患者”ではなく、ともに影響を与え合う一人の人間であるとの眼差しが通底している。
映画を観る私たちはどうか。無意識のうちに「あちら」と「こちら」で線を引いてはいないか。安楽死の是非を云々した人たちはどうか。死を選択肢に入れるという残酷な提案をためらいもなくできるのは、自分は無関係だと思っているからではないだろうか。
タイトルにある杳(よう)という漢字は、木の下に日が沈んだようすをあらわす。「暗くてはっきりしない」「奥が深い」「はるかに遠い」などの意味があるという。夜と朝が溶け合いつながっているように、この社会に生きる私たちの間にも互いを分かつ境界線はないと感じた。
エンドロールで流れた音楽にも心を震わされた。タイトルは「たよりないもののために」。ひっそりと息づくように流れるイントロ、か細く高い歌い出し、歌詞に込められた表現の一つひとつを聴きながら、とっさに「痛みを知っている人の歌だ」という言葉が浮かんだ。
映画「杳かなる」は日本各地で順次公開。ぜひ、本編を観た上で改めてこの歌を聴いてほしい。(理)
「杳かなる」
監督・撮影・編集:宍戸大裕/ナレーション・主題歌:寺尾紗穂/撮影:高橋愼二/2024年/日本/124分/企画・制作:映画『杳かなる』製作委員会/宣伝・配給:映画『杳かなる』上映委員会
公式サイト(https://harukanaru.com/)
※月刊イオ3月号掲載の記事に加筆・修正しました。